- なぜワトソンークリック型塩基対が重要か
- TATA ボックス結合タンパク質はDNAの副溝に結合し、DNAらせんを曲げる。DNAのどんな性質によって、TATA ボックス結合タンパク質がDNA らせんを認識できるか
- 二本鎖環状プラスミドの塩基配列決定には、相補的で短い一本鎖オリゴヌクレオチド DNAプライマーをプラスミドに結合させる、このため、ふつうはプラスミドとプライマーを 90°Cに加熱し、その後、ゆっくりと温度を25°Cにする。この方法がうまくいくのはなぜか。
- RNAとDNAのどんな違いが、DNAのほうがずっと安定である理由か。DNAの機能に安定性はどんな意味をもつか。
- 原核生物と真核生物のmRNAについて、その合成のされ方と構造にはどんな違いがあるか
- ヒトの特定の増殖因子受容体遺伝子の機能を究中に、この遺伝子から 2種類のタンパク質が合成されることがわかった。大きいほうのタンパク質は膜貫通ドメインをもち、細胞表面で増殖因子を認識する。この結果、下流のシグナル伝達経路が活性化される。これに対して、小さいほうのタンパク質は、細胞から分泌され、血中にあって循環している増殖因子に結合する。この結果、下流のシグナル伝達経路が阻害される。細胞はどうやってこの二つの違ったタンパク質を合成するか。
- 多くの細菌遺伝子の転写は、オペロンという機能単位で行われる。トリプトファンオペロンがそうした例である。オペロンとは何か。真核生物の遺伝子の配置と比べて,遺伝子をオペロンに組織化する利点は何か。
- 細菌、真核生物、ポリオウイルスで,翻訳開始部位の選択がどのようになされるか、比較せよ。
- 大サブユニット中の23SrRNAにペプチジルトランスフェラーゼ活性があるという証拠は何か
- ポリ(A)結合タンパク質Iの変異は翻訳にどんな影響を与えるか。こうした変異体からとったポリソームの電子顕微鏡写真は、正常なものと比べて差があるか。
- DNA 合成は不連続だという事実から、どんな特徴をもつDNAが生じるか。細胞は岡崎フラグメントやDNAリガーゼをどのように用いているか。
- 真核生物は、DNA 複製の誤りや変異原にさらされることで起こる突然変異を防ぐ修復機構をもっている。真核細胞にある3種類の除去修復機構とは何か、UV照射でDNAに生じる傷害であるチミンーチミンニ量体を修復するのは、このうちどれか。
- 高い頻度で変異を生じる事態が起こるにもかかわらずDNA 修復系が遺伝子の正確さを維持している。(a)UV照射、そして(b)電離放射線照射で、どのようなDNAの変異が生じるか、哺乳類細胞におけるこうした変異を修復する機構について解説せよ.こうした修復系の機構が失われるような変異が多くのがん化の特徴である理由を推論せよ。
- DNA傷害を修復するとともに遺伝的多様性獲得にも寄与する過程はなんとよぶか。この二つの過程はどこが似ており、どこが違うか。
- レトロウイルスのゲノムは宿主細胞ゲノムに挿入される。レトロウイルスに固有の遺伝子は何か。なぜこの遺伝子でコードされるタンパク質が、レトロウイルスの生活環を維持するのに必須なのか。多くのレトロウイルスがある種のヒト細胞に感染する。そうしたもののうち二つをあげ、この感染でどんな医学的問題が生じるか述べよ。なぜこうしたウイルスは特定の細胞だけに感染するのか。
なぜワトソンークリック型塩基対が重要か
- 遺伝情報の正確な保存と伝達
- DNAの安定な二重らせん構造の維持
- 遺伝子発現やタンパク質合成の基盤
- 分子生物学の中心的な概念(セントラルドグマ)
- ワトソンークリック型塩基対の発見は、DNA→RNA→タンパク質という生命の情報伝達の仕組み(セントラルドグマ)の理解に不可欠でした。
まとめ
TATA ボックス結合タンパク質はDNAの副溝に結合し、DNAらせんを曲げる。DNAのどんな性質によって、TATA ボックス結合タンパク質がDNA らせんを認識できるか
TATAボックス結合タンパク質(TBP)がDNAらせんを認識できる理由
- TATAボックス配列の特徴
TATAボックスは、アデニン(A)とチミン(T)が多く並ぶ特徴的な配列(例:TATAAA)です。この配列はDNAの二重らせんの中でも特に柔軟性が高く、構造が曲がりやすい性質を持っています。 - 水素結合の少なさによる安定性の低さ
A-T塩基対はG-C塩基対に比べて水素結合が2本と少なく、二重らせんの安定性が低い部分です。このため、TATAボックス領域は他の配列よりも二重らせんがほどけやすく、タンパク質が結合しやすくなっています。 - 副溝の化学的特徴
TBPはDNAの副溝(マイナーグルーブ)に結合します。TATAボックス配列の副溝部分は、塩基の並びによって特有の形状や化学的性質(例えば水素結合供与体・受容体の配置)を持っています。TBPはこの副溝の特徴を認識し、特定のアミノ酸残基を使って選択的に結合します。 - 配列の柔軟性と曲げやすさ
TATAボックス配列はDNAが曲がりやすく、TBPが結合すると約80度も鋭く折れ曲がります。この曲げやすさも、TBPがTATAボックスを選択的に認識する重要な要因です。 - アミノ酸残基との相互作用
TBPは、フェニルアラニンなどのアミノ酸残基を副溝に差し込むことで、DNAの構造を局所的に変化させ、より強固に結合します。さらに、リジンやアルギニンなどの正電荷を持つアミノ酸が、DNAのリン酸骨格の負電荷と静電的に相互作用することで、結合の安定性が高まります。
まとめ
TATAボックス結合タンパク質がDNAらせんを認識できるのは、TATAボックス配列がもつ「A-T塩基対の多さによる柔軟性と安定性の低さ」「副溝の特有な化学的特徴」「曲げやすさ」など、DNA自体の物理的・化学的性質によるものです。これらの性質が組み合わさることで、TBPはTATAボックスを高い特異性で認識し、転写開始の目印となる役割を果たしています。
二本鎖環状プラスミドの塩基配列決定には、相補的で短い一本鎖オリゴヌクレオチド DNAプライマーをプラスミドに結合させる、このため、ふつうはプラスミドとプライマーを 90°Cに加熱し、その後、ゆっくりと温度を25°Cにする。この方法がうまくいくのはなぜか。
原理と理由
- 高温(90°C)で加熱する理由
- ゆっくり冷却する理由
- 25°Cでのアニーリング
- 最終的に25°C程度まで冷却することで、プライマーとDNAが水素結合によってしっかりと結合した状態になります。
- これにより、後続のDNA合成や塩基配列決定反応のための「出発点」が正確に用意されます。
まとめ
この方法がうまくいく理由は、
- 高温でDNAを完全に一本鎖化し、プライマーが結合できるようにすること
- ゆっくり冷却することで、プライマーが標的配列に正確に結合すること
にあります。これにより、塩基配列決定やPCRなどの反応で高い特異性と効率が得られます。
RNAとDNAのどんな違いが、DNAのほうがずっと安定である理由か。DNAの機能に安定性はどんな意味をもつか。
RNAとDNAのどんな違いが、DNAのほうがずっと安定である理由か
1. 構造的な違い
- 二本鎖構造 vs. 一本鎖構造
DNAは通常、二本鎖の二重らせん構造をとるのに対し、RNAはほとんどが一本鎖です。二本鎖のDNAは相補的な塩基対(水素結合)でしっかり結ばれ、外部からの侵襲に対しても構造的に安定です。 - 糖の違い(2’位の水酸基)
DNAはデオキシリボース(2’位はH)をもち、RNAはリボース(2’位に-OH)を持ちます。RNAの2’OHグループは加水分解や化学反応を受けやすく、これがRNAを不安定にしています。逆に、DNAの2’位に-OHがないことで加水分解に強く、長期的に安定です。 - 塩基の違い
DNAはチミン(T)を、RNAはウラシル(U)を持ちます。チミンはウラシルよりも分子構造的に安定で、その結果DNAがより長期間安定でいられます。 - ヒストンとの複合体
DNAはヒストンなどのタンパク質と結合し、クロマチン構造を形成することで外部環境から守られています。
2. 化学的な違い
- 水素結合と塩基対形成
DNAの二重らせん構造では多数の水素結合、塩橋、ファンデルワールス力等の非共有結合で安定性が高まっていますが、RNAは主に一本鎖で安定したヘリックスが作りにくいです。 - 分解酵素の影響
RNAは細胞内外に豊富なRNase(分解酵素)が存在するため、分解されやすいですが、DNAは比較的分解酵素に強く保存されます。
DNAの機能に安定性はどんな意味をもつか
- 遺伝情報の長期保存
DNAは細胞および生物種の世代を超えて遺伝情報を正確に保存する必要があります。そのため、高い化学的・構造的安定性は、遺伝子が損傷や変異を受けにくくし、生命の「設計図」を守ります。 - 誤りの修復と維持
DNAは損傷した場合に修復メカニズム(DNA修復)が働きやすい構造であり、安定な基盤があることがエラーの蓄積を最小限に抑えます。 - 複製・分配の精度
安定なDNAは正確な複製と細胞分裂(有糸分裂・減数分裂)が可能です。これにより次世代に誤りなく遺伝情報が伝えられます。 - 遺伝子発現制御の基盤
安定に保たれたDNAから、必要に応じてRNAが転写・合成されます。RNAは比較的短寿命で、細胞がリアルタイムで環境変化に応じて遺伝子発現を調整するための可逆的な素材となっています。
まとめ表
| 違い | DNA | RNA |
|---|---|---|
| 主な構造 | 二本鎖(らせん) | 一本鎖 |
| 糖の種類 | デオキシリボース | リボース |
| 2’位の官能基 | H(安定) | OH(不安定、加水分解を促進) |
| 特有の塩基 | チミン | ウラシル |
| 安定性 | 非常に高い | 低い |
| 生体内での寿命 | 非常に長い | 短い |
| 主な役割 | 遺伝情報の保存 | 情報の伝達・一時的役割 |
DNAの高い安定性は、生命の根幹である遺伝情報の長期保存と、正確な情報伝達・維持に決定的な役割を果たしています。
原核生物と真核生物のmRNAについて、その合成のされ方と構造にはどんな違いがあるか
合成のされ方(転写と翻訳の違い)
原核生物のmRNA
- 合成場所
原核生物では細胞に核がなく、mRNAの合成(転写)は細胞質で行われます。 - 転写と翻訳の同時進行
mRNAが合成されるとすぐにリボソームが結合し、転写と翻訳が同時に開始される(同時進行型)。 - オペロン構造
1本のmRNAに複数の遺伝子が並ぶ「ポリシストロニック(polycistronic)」型が多く、これにより複数のタンパク質が一つのmRNAから合成されます。 - 合成酵素
1種類のRNAポリメラーゼが全てのRNA(mRNA、rRNA、tRNA)を合成します。
真核生物のmRNA
- 合成場所
mRNAの転写は核内で行われ、その後細胞質へ輸送されます。 - 転写と翻訳の分離
転写が完全に終わってから翻訳が始まる(時空間分離型)。 - モノシストロニック
ほとんどのmRNAは1つのタンパク質のみをコードする「モノシストロニック(monocistronic)」型。 - 合成酵素
RNAポリメラーゼⅡがmRNAの合成を担い、他にも複数種類のRNAポリメラーゼがあります。
mRNA構造の違い
詳細な違い
- 5’キャップ・ポリAテール(真核生物のみ)
5’末端にキャップ構造、3’末端にポリAテールが付加されるため、安定性が向上し、翻訳効率や核外輸送に重要。 - スプライシング(真核生物のみ)
イントロンと呼ばれる不要配列が切り取られ、エキソンのみが連結されて成熟mRNAとなる。 - 寿命と安定性
原核生物mRNAは非常に短寿命だが、真核生物mRNAはキャップやテールのおかげで安定して長持ちする。 - 翻訳開始の仕組み
原核生物は位置特異的なシャイン–ダルガルノ配列がリボソームの結合目印となる。一方、真核生物は5’キャップ周辺をリボソームが探索し、開始コドンを型どる。
まとめ
- 原核生物mRNAは合成と翻訳が同時・同所で起こり加工がほぼなく、寿命が短く、多くはポリシストロニック型です。
- 真核生物mRNAは核内で前駆体が合成され、多段階の修飾・スプライシングを経て核外に運ばれ、1本で1つのタンパク質だけをコードするのが一般的です。
- これらの違いは細胞内の構造や遺伝子発現制御の複雑さと密接に関係します。
ヒトの特定の増殖因子受容体遺伝子の機能を究中に、この遺伝子から 2種類のタンパク質が合成されることがわかった。大きいほうのタンパク質は膜貫通ドメインをもち、細胞表面で増殖因子を認識する。この結果、下流のシグナル伝達経路が活性化される。これに対して、小さいほうのタンパク質は、細胞から分泌され、血中にあって循環している増殖因子に結合する。この結果、下流のシグナル伝達経路が阻害される。細胞はどうやってこの二つの違ったタンパク質を合成するか。
細胞が2種類の違ったタンパク質を合成する仕組み
1. 選択的スプライシング(Alternative Splicing)
- このように一つの遺伝子から異なる性質をもつ2種類のタンパク質が作られる現象は、主に「選択的スプライシング」と呼ばれる遺伝子制御メカニズムによって説明できます。
- mRNAの前駆体(pre-mRNA)から異なるエクソンの組み合わせを選択してスプライス(切り貼り)することで、「膜貫通型タンパク質」と「分泌型タンパク質」という機能の異なる産物が作り分けられます。
2. 構造の違いが機能の違いに
- 大きいほう(膜貫通型):
このタンパク質は膜貫通ドメインを持つようなスプライシングバリアントで合成され、細胞膜に局在し、増殖因子のシグナルを細胞内へ伝える役割を果たします。 - 小さいほう(分泌型):
別のスプライシングバリアントでは膜貫通ドメインが除かれ、代わりに分泌シグナルを持つ可溶型タンパク質として合成されます。このタンパク質は細胞外(血中)に分泌され、循環する増殖因子を“キャッチ”してシグナルの活性化を間接的に阻害します。
3. 具体例
4. まとめ
| タンパク質 | 合成メカニズム | 形 | 主な機能 |
|---|---|---|---|
| 膜型(大きいほう) | スプライシングで膜貫通ドメインを含む | 膜貫通型 | 細胞表面で増殖因子を認識し、シグナル伝達を活性化 |
| 分泌型(小さいほう) | スプライシングで膜貫通ドメインなし | 分泌・可溶型 | 血中の増殖因子を結合してシグナルを阻害 |
- **まとめると、細胞が一つの遺伝子から二つの異なる機能を持つタンパク質を作り分ける仕組みの中心は、mRNAの選択的スプライシングにあります。**この調節によって、環境や細胞の状態、組織の種類に応じてタンパク質の形と機能を柔軟に変化させることが可能となっています。
多くの細菌遺伝子の転写は、オペロンという機能単位で行われる。トリプトファンオペロンがそうした例である。オペロンとは何か。真核生物の遺伝子の配置と比べて,遺伝子をオペロンに組織化する利点は何か。
オペロンとは
- オペロンとは、一つのプロモーター(転写開始点)の支配下でまとめて転写される、機能的に関連した複数の遺伝子群からなるDNAの単位です。
- オペロンに含まれる遺伝子は隣接して配置されており、**一つのmRNA(ポリシストロニックmRNA)**としてまとめて転写されます。
- 典型的な例は、トリプトファンオペロンやラクトースオペロンなどが知られています。
真核生物の遺伝子配置との違い
| 生物群 | 遺伝子配置の特徴 | mRNAの型 |
|---|---|---|
| 原核生物 | 機能の関連する複数の遺伝子がオペロンとして隣接 | ポリシストロニック |
| 真核生物 | ほとんどの遺伝子が個別にプロモーターで制御される | モノシストロニック |
オペロンに遺伝子を組織化する利点
- 効率的な遺伝子発現調節
機能的に関連する遺伝子をひとまとめにして「ON/OFF」を同時に切り替えられる。例:代謝経路に必要な全ての酵素を一括で調節可能。 - 迅速な環境応答
栄養素や代謝物の有無に応じて、必要な一連のタンパク質を一気に合成・停止できるため、エネルギーの無駄を省き素早く適応できる。 - 遺伝子発現の協調性・連動性
同じmRNAから複数のタンパク質が同時に作られるため、経路全体としての機能がタイミングよく発揮できる。
真核生物にはオペロンがないことの意味
ポイントまとめ
- オペロンは、原核生物が関連遺伝子をまとめて転写・発現させるためのユニット。
- 遺伝子をオペロンに組織化することで、「同時」「効率的」「一括」な調節が可能。
- 真核生物では、個々の遺伝子が独立して調節されるため、オペロンの利点は見られません。
細菌、真核生物、ポリオウイルスで,翻訳開始部位の選択がどのようになされるか、比較せよ。
細菌(原核生物)の翻訳開始部位の選択
- 細菌のmRNAは、開始コドン(通常AUG)の直前にShine-Dalgarno配列(SD配列、AGGAGGUなど)を持つことが多く、この配列がリボソームの16S rRNAと相補的に結合することで、リボソームの小サブユニットがmRNA上の適切な位置に誘導される。
- SD配列と16S rRNAの相互作用によって、開始コドンがリボソームのP部位に正確に配置され、翻訳が開始される。
- 一つのmRNA中に複数の翻訳開始部位が存在することも多く(ポリシストロニックmRNA)、それぞれ自律的に翻訳開始が行われる。
真核生物の翻訳開始部位の選択
- 真核生物のmRNAは5’キャップ構造(7-メチルグアノシンキャップ)を持ち、リボソームはまずこのキャップに結合する。
- リボソーム小サブユニットと翻訳開始因子が複合体を形成し、mRNAの5’末端から3’方向に「スキャニング」して最初に見つかるAUG開始コドンを特定する。
- 周辺配列が**コザック配列(GCCRCC AUG G)**に近いと、効率的な翻訳開始が促進される。
- ほとんどの真核生物mRNAはモノシストロニック(1つのポリペプチドのみ)であり、翻訳開始は原則1箇所で厳密に制御されている。
ポリオウイルスの翻訳開始部位の選択
- ポリオウイルスはプラス鎖一本鎖RNAウイルスであり、そのウイルスRNAには**配列内リボソーム進入部位(IRES:Internal Ribosome Entry Site)**が存在する。
- このIRESの働きにより、mRNAの5’キャップ構造がなくても、リボソームが直接mRNA内部の特定部位に結合して翻訳を開始できる。
- IRESは、ウイルス感染細胞のmRNA翻訳を抑制しながら、自ウイルスmRNAの翻訳を効率的に進める独自の戦略として機能している。
比較表
| 生物・ウイルス | 翻訳開始部位の選択機構 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 細菌(原核生物) | Shine-Dalgarno配列+開始コドン | SD配列でリボソーム位置決定、複数箇所可 |
| 真核生物 | 5’キャップスキャニング+コザック配列 | 最初のAUG(+配列文脈)が標的、ほぼ1箇所 |
| ポリオウイルス | IRES依存的内部結合 | 5’キャップ不要、IRES部位から直接開始 |
まとめ
- 細菌はSD配列による位置特定で、1本のmRNA上で複数の翻訳開始部位が存在することもある。
- 真核生物はキャップ依存スキャニングと配列文脈(コザック配列)で翻訳開始部位を厳密に決定し、1本のmRNAに対し多くは1つの開始部位のみ。
- ポリオウイルスはIRESによるキャップ非依存的な機構をもち、ウイルス特有の柔軟な翻訳開始方法をとる。
このように、翻訳開始部位の選択は、進化や生活環境に応じて生物ごとに多様なメカニズムが発達しています。
大サブユニット中の23SrRNAにペプチジルトランスフェラーゼ活性があるという証拠は何か
1. タンパク質の極端除去実験
- リボソームの50S大サブユニットからほとんどのリボソームタンパク質を除去しても、23S rRNAがほぼ単独でも**ペプチジルトランスフェラーゼ活性(ペプチド結合形成)**を保持することが示されました。
- RNAを特異的に破壊すると活性が失われたことから、タンパク質でなくRNA自身が触媒の本体であることがわかりました。
2. 遺伝学的証拠と変異体解析
- 23S rRNA中の特定のヌクレオチド(例:A2451やG2553など)を変異させると、ペプチジルトランスフェラーゼ活性が低下または喪失します。特にA2451は保存性が高く、この塩基の化学的修飾や変異で活性が大きく障害されます。
- これらの変異はリボソーム全体の機能不全やタンパク質合成停止を引き起こすことから、23S rRNAの特定領域が触媒機能に必須であることが明らかです。
3. 化学修飾・クロスリンク実験
4. 結晶構造解析
- X線結晶構造解析により、リボソームのペプチジル移転反応中心(Peptidyl Transferase Center, PTC)はほぼ全て23S rRNAで構成されており、タンパク質は半径18Å以内に存在しないことが明確になっています。
5. 人工合成23S rRNAによる触媒活性の再現
まとめ表
| 証拠の種類 | 内容・代表的な結果 |
|---|---|
| タンパク質極限除去 | 23S rRNA主体でも活性維持、RNA破壊で消失 |
| 遺伝学的・変異体解析 | 特定ヌクレオチド変異で活性消失 |
| 化学修飾・クロスリンク | 基質tRNAと23S rRNAが直接架橋 |
| 結晶構造解析 | 触媒中心はほぼ全て23S rRNA |
| 体外合成23S rRNA活性 | ドメインVのみ/人工23S rRNAでも活性検出 |
これらの実験的証拠から、リボソームの大サブユニットに存在する23S rRNAがペプチジルトランスフェラーゼ活性=ペプチド結合形成反応を担う「リボザイム」として機能していることが確立されています。
ポリ(A)結合タンパク質Iの変異は翻訳にどんな影響を与えるか。こうした変異体からとったポリソームの電子顕微鏡写真は、正常なものと比べて差があるか。
ポリ(A)結合タンパク質Iの変異が翻訳に与える影響
- ポリ(A)結合タンパク質I(PABP、PAB1)はmRNAの3’末端ポリ(A)配列に結合し、eIF4Gなどの翻訳開始因子と相互作用することで、リボソームのリクルートやmRNAの循環化を促進し、翻訳開始と全体的な翻訳効率を高める役割を果たしています。
- PABPに変異が生じると、PABPとeIF4Gまたは他の因子の相互作用が障害されるため、翻訳効率が大幅に低下し、リボソーム開始複合体(48Sおよび80S)の形成が阻害されます。
- また、変異によりPABPの多量体形成(ポリ(A)鎖上での直鎖的配置)ができなくなると、in vitro 翻訳活性が低下することも報告されています。
- PABP活性が低下した細胞では、mRNAの安定性や翻訳開始自体が十分に行われず、タンパク質合成全体が減少します。
ポリソームの電子顕微鏡写真の変化
- 野生型PABPをもつ細胞のポリソームは、多くのリボソームがmRNA上に密に並んでいる典型的な「ポリソーム構造」を電子顕微鏡で示します。
- 一方、PABP変異体細胞やPABPが欠損した条件下では、mRNA上に結合しているリボソームの数が著しく減少し、ポリソームが形成されにくくなります。
- 電子顕微鏡で観察すると、正常細胞に比べて「ポリソームの密度が低い」「短いポリソーム(リボソームが少ない)」などの明らかな違いが確認できます。
- これは、翻訳開始効率の低下を反映しており、PABPの機能障害がリボソームの連続的結合(ポリソーム形成)を妨げるためです。
まとめ
- ポリ(A)結合タンパク質Iの変異は、翻訳開始と全体的な翻訳効率を大きく低下させ、リボソームがmRNA上で密に連なる通常のポリソーム構造が十分に形成できなくなります。
- その結果、変異体のポリソーム電子顕微鏡写真は、正常なものよりもリボソームが少なく、密度の低いポリソーム像となる、という明確な違いを示します。
DNA 合成は不連続だという事実から、どんな特徴をもつDNAが生じるか。細胞は岡崎フラグメントやDNAリガーゼをどのように用いているか。
不連続なDNA合成によるDNAの特徴
- 岡崎フラグメントの生成
DNA複製は常に「5’→3’方向」で新しい鎖が合成されますが、二本鎖DNAは逆向きになっているため、片方(ラギング鎖)は短い断片(岡崎フラグメント)として不連続に合成されます。 - 断片的な新生DNA鎖
合成直後のラギング鎖は、数百~数千塩基ごとに途切れた短いDNA断片(岡崎フラグメント)と、それらの間に「RNAプライマー」が挟まった状態になっています。 - 最初は多数の“つなぎ目”をもつ
合成の途中段階のラギング鎖DNAは、多数の未連結なフラグメント=“つなぎ目”をもつ状態です。
岡崎フラグメントとDNAリガーゼの役割
1. 岡崎フラグメントの形成
- 岡崎フラグメントは、DNAポリメラーゼが「RNAプライマー」の3’末端から順次合成を始めることで生じます。
- ラギング鎖では、多数のRNAプライマーが定期的に新たに合成され、それぞれから短いDNA断片がつくられるため、岡崎フラグメントが連続して生成されます。
2. RNAプライマーの除去
- 合成後、岡崎フラグメントに付随しているRNAプライマーは「RNase H」や「DNAポリメラーゼI」などの酵素によって取り除かれます。
- 欠損した部分は、DNAポリメラーゼによって新たなDNAに置き換えられます。
3. DNAリガーゼによる連結
- 最後に「DNAリガーゼ」が岡崎フラグメント同士の“つなぎ目”を共有結合でしっかりと連結します。
- こうして、ラギング鎖の断片(フラグメント)がひとつながりの連続したDNA鎖に仕上げられます。
まとめ表
| 合成段階 | 断片の状態 | 主要酵素 | 主な役割 |
|---|---|---|---|
| 合成直後 | 岡崎フラグメント+RNAプライマー | DNAポリメラーゼ、プライマーゼ | 5’→3’方向への断片的な合成 |
| RNAプライマーの除去 | DNAのみに | RNase H, ポリメラーゼI | RNAプライマーの除去と“穴埋め”DNA合成 |
| 連結 | つなぎ目が埋まる | DNAリガーゼ | フラグメント間のリン酸骨格の形成 |
- DNA合成の不連続性は、岡崎フラグメントの生成と、その後のRNA除去・リガーゼによる連結という多段階処理により、最終的には途切れのない“連続したDNA鎖”へと仕上げられるのが特徴です。
- これらの過程が正確に行われることで、複製されたDNAは情報の欠落や転写ミスなしに後世へと受け継がれます。
真核生物は、DNA 複製の誤りや変異原にさらされることで起こる突然変異を防ぐ修復機構をもっている。真核細胞にある3種類の除去修復機構とは何か、UV照射でDNAに生じる傷害であるチミンーチミンニ量体を修復するのは、このうちどれか。
真核細胞にある3種類の除去修復機構
- 塩基除去修復(Base Excision Repair:BER)
- 損傷や変異を受けた1個の塩基だけを選択的に切り出し、正常な塩基に置き換える仕組みです。脱アミノ化や酸化、アルキル化など、主に小さな損傷に対応します。
- ヌクレオチド除去修復(Nucleotide Excision Repair:NER)
- 異常な塩基や構造的な歪みがある場合、その部分を数個のヌクレオチドごとまとめて除去し、正常なDNAを合成して修復します。紫外線によるピリミジン二量体やバルキーアジュバント(大きな付加体)などに対応できる機構です。
- ミスマッチ修復(Mismatch Repair:MMR)
- DNA複製直後に生じた2本鎖間の塩基のミスマッチ(誤対合)や短い挿入・欠失などを認識し、正しい配列に修正する仕組みです。
チミンーチミン二量体の修復に働く除去修復機構
- 紫外線(UV)照射によって生じる「チミンーチミン二量体(ピリミジン二量体)」の修復には、**ヌクレオチド除去修復(NER)**が主に働きます。
- チミン二量体はDNAの構造に大きな歪みを起こすため、NERがこのような大きな損傷を認識し、異常部位を含む数個のヌクレオチドを切り取った後に、DNAを修復します。
まとめ表
| 修復機構 | 主な対象損傷 | チミン二量体の修復 |
|---|---|---|
| 塩基除去修復(BER) | 小さな塩基損傷 | × |
| ヌクレオチド除去修復(NER) | 大きな構造変化やUV損傷 | 〇 |
| ミスマッチ修復(MMR) | 塩基対ミスマッチ | × |
ポイント
- 真核細胞には「塩基除去修復(BER)」「ヌクレオチド除去修復(NER)」「ミスマッチ修復(MMR)」の3つの除去修復機構がある。
- UVによって生じるチミン二量体を修復するのは、「ヌクレオチド除去修復(NER)」である。
高い頻度で変異を生じる事態が起こるにもかかわらずDNA 修復系が遺伝子の正確さを維持している。(a)UV照射、そして(b)電離放射線照射で、どのようなDNAの変異が生じるか、哺乳類細胞におけるこうした変異を修復する機構について解説せよ.こうした修復系の機構が失われるような変異が多くのがん化の特徴である理由を推論せよ。
(a)UV照射で生じるDNA変異と修復機構
- 主なDNA損傷・変異
- 主な修復機構
(b)電離放射線照射で生じるDNA変異と修復機構
- 主なDNA損傷・変異
- 主な修復機構
DNA修復機構の消失とがん化の関連
- DNA修復不全とがん化
- がん化を引き起こす理由の推論
| 損傷要因 | 主なDNA損傷/変異 | 哺乳類細胞の修復機構 | 修復喪失時の帰結 |
|---|---|---|---|
| UV照射 | ピリミジン二量体、光産物、点突然変異(C→T, CC→TT) | ヌクレオチド除去修復(NER) | 皮膚がん、色素性乾皮症 |
| 電離放射線 | 主としてDSB・SSB、塩基損傷 | HRR、NHEJ、BER | 染色体異常、複雑ながん化 |
DNA傷害を修復するとともに遺伝的多様性獲得にも寄与する過程はなんとよぶか。この二つの過程はどこが似ており、どこが違うか。
このような過程は**「遺伝的組換え(特に相同組換え)」**と呼ばれます。
相同組換え(Homologous Recombination, HR)は、DNA二重鎖切断などの傷害を修復する主要な仕組みであると同時に、減数分裂期に遺伝的多様性を生み出す根幹的なメカニズムです。
二つの過程(DNA修復と遺伝的多様性獲得)の共通点と相違点
共通点(似ている点)
- 利用する分子メカニズムが同じ
- どちらもDNAの「相同な配列(姉妹染色分体や相同染色体)」を鋳型として利用し、DNA鎖の切断部分を正確に修復・再構築します。
- 主要タンパク質・酵素が共通
- Rad51などの組換えタンパク質が、傷害修復でも減数分裂でも働きます。
- 高い正確性
相違点(異なる点)
| 項目 | DNA修復における組換え | 遺伝的多様性獲得(減数分裂時) |
|---|---|---|
| 主な目的 | 損傷(例:二本鎖切断)の正確な修復 | 新しい遺伝子組み合わせの創出 |
| 発生タイミング | 体細胞周期全般 | 減数分裂期(配偶子形成) |
| 使用する鋳型 | 主に姉妹染色分体 | 主に父母由来の相同染色体 |
| 結果 | 配列情報の保存(変化させない) | クロスオーバーによる配列の入れ替え |
| 生物学的意義 | ゲノム安定性・突然変異防止 | 集団内の多様性増進、進化原動力 |
ポイントまとめ
- 「相同組換え」は、DNA修復機構としても、遺伝的多様性創出機構としても中心的役割を担っている。
- 仕組み(ホモロジー利用、主なタンパク質)は共通でも、目的と顕現する結果が大きく異なります。
- この機構があるからこそ、生物はゲノムの安定性と進化的適応力の双方を両立させています。
レトロウイルスのゲノムは宿主細胞ゲノムに挿入される。レトロウイルスに固有の遺伝子は何か。なぜこの遺伝子でコードされるタンパク質が、レトロウイルスの生活環を維持するのに必須なのか。多くのレトロウイルスがある種のヒト細胞に感染する。そうしたもののうち二つをあげ、この感染でどんな医学的問題が生じるか述べよ。なぜこうしたウイルスは特定の細胞だけに感染するのか。
レトロウイルスに固有の遺伝子
- レトロウイルスのゲノムには、gag、pol、env という3つの主要な遺伝子が共通に存在し、**逆転写酵素(reverse transcriptase)**をコードするpol遺伝子がとくにレトロウイルスに固有です。
- gag:カプシド(殻)タンパク質などの構造タンパク質
- pol:逆転写酵素(Reverse Transcriptase)、インテグラーゼ(Integrase)、プロテアーゼなどの酵素
- env:エンベロープ(外膜)タンパク質
固有遺伝子でコードされるタンパク質が必要な理由
- 逆転写酵素は、ウイルスゲノムのRNAをDNAにコピー(逆転写)する機能を持ちます。DNAに変換されたウイルス遺伝子は、インテグラーゼによって宿主ゲノムに挿入されます。
- 逆転写酵素がなければウイルスRNAをDNAへ変換できず、宿主ゲノムへの組み込みができないため、ウイルスの複製と増殖サイクルが成立しません。
- インテグラーゼもまた、変換されたウイルスDNAを宿主染色体へ「切って貼る」役割を担い、生活環を完結させるのに不可欠です。
ヒト細胞に感染する主なレトロウイルスと医学的問題
| ウイルス名 | 主な感染細胞 | 生じる医学的問題 |
|---|---|---|
| HIV(ヒト免疫不全ウイルス) | 主にCD4陽性Tリンパ球 | 後天性免疫不全症候群(AIDS)、免疫力低下による日和見感染や腫瘍 |
| HTLV-1(ヒトT細胞白血病ウイルス1型) | 主にCD4陽性Tリンパ球 | 成人T細胞白血病(ATL)、HAM(HTLV-1関連脊髄症)、ブドウ膜炎など |
- HIV感染:免疫細胞(CD4陽性T細胞)が破壊されて免疫力が大幅に低下し、さまざまな日和見感染症(カリニ肺炎、真菌感染など)や悪性腫瘍が発症します。治療しない場合はAIDSに進行します。
- HTLV-1感染:長期的な潜伏ののち、一部の感染者で白血病(ATL)や神経障害(HAM)が発症します。日本(特に九州地方)を含む世界の特定地域で流行し、根治は難しいとされています。
なぜレトロウイルスは特定の細胞だけに感染するのか
- レトロウイルスのエンベロープタンパク質(envがコード)は感染対象の細胞膜上に存在する**特定の受容体(レセプター)**と結合しなければ侵入できません。
- 例えばHIVはCD4分子とCCR5/CXCR4といった共受容体を持つTリンパ球などにしか結合・侵入できません。
- HTLV-1も特定の表面マーカーを持つT細胞を主な標的とするなど、「ウイルスの表面タンパク質」と「細胞側の受容体」の**“鍵と鍵穴”**の関係により感染範囲が決まります。
まとめ
- レトロウイルスはgag, pol, envの3遺伝子が共通であり、特にpol(逆転写酵素)がウイルス生活環で不可欠。
- HIVやHTLV-1はヒトにとって重大な病気(AIDSや白血病等)の原因となる。
- 特定の細胞だけに感染するのは、ウイルスの表面タンパク質が特定の細胞受容体としか結合できないからである。
問題文引用元:東京化学同人 分子細胞生物学 第6版
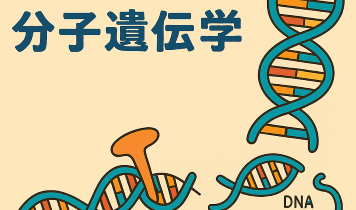
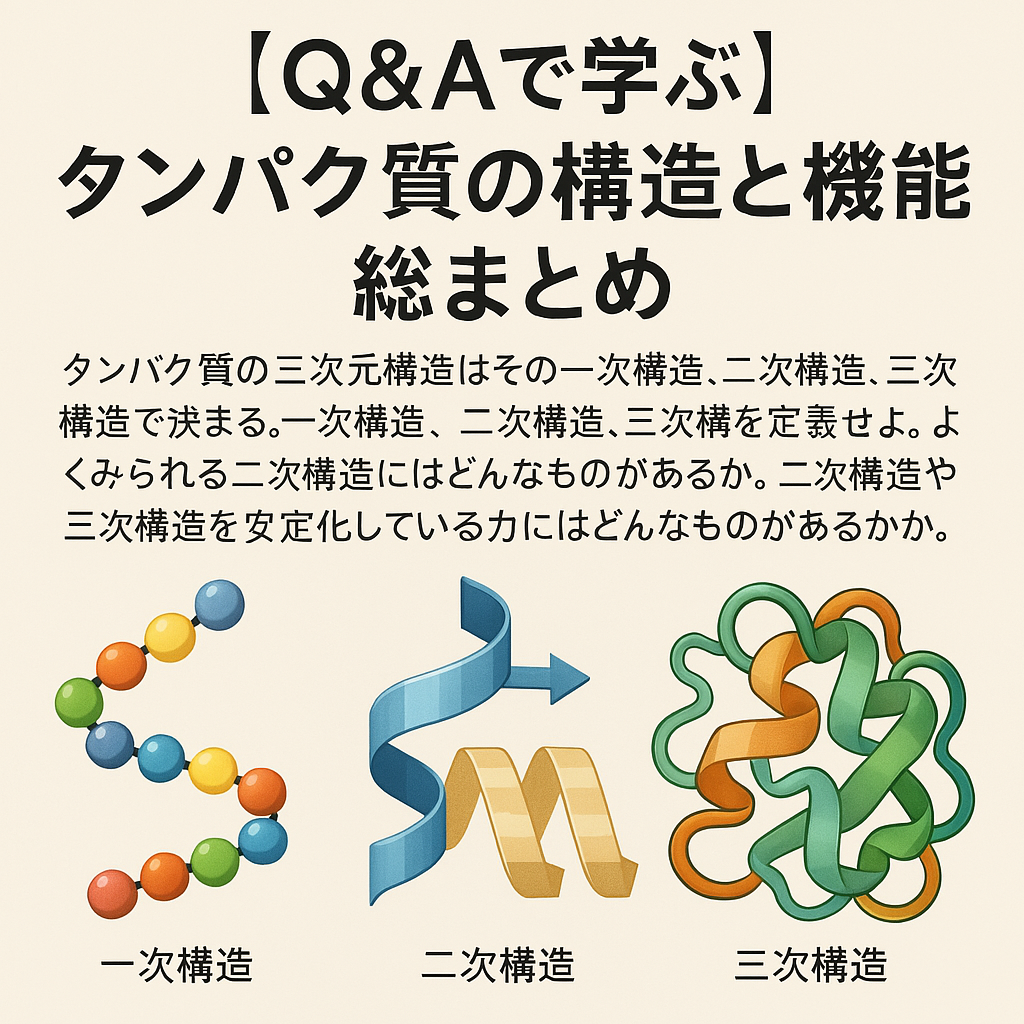
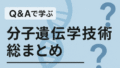
コメント