- 遺伝子突然変異によって、複雑な細胞内過程や発生過程の機構を解明することができる。劣性変異と優性変異では、遺伝学的解析にどのような違いが表れるか。
- 必須遺伝子の機能を研究するにあたって、温度感受性変異はなぜ重要か。また、これをどのように利用するか。例をあげよ。
- 2つの変異が同じ遺伝子に起こったのか、別の遺伝子に起こったのかを調べるのに、どのように相補性検定を使うか。優性変異ではこれが使えないのはなぜか。説明せよ。
- 抑制変異と合成致死変異の使い方の違いを比較せよ。
- 制限酵素とDNAリガーゼはDNAクローニングに欠かせない.制限酵素を産生している細菌はなぜ自身のDNAを分解しないのか。制限部位の一般的な特徴をあげよ。制限酵素でDNAを分解したとき生じる、3種類の末端はどんなものか。DNAリガーゼはどんな反応を触媒するか。
- 細菌のプラスミドはクローニングベクターに使える。プラスミドベクターで必須な要素は何か。プラスミドをクローニングベクターとして使うときの利点と応用例をあげよ。
- DNAライブラリーはクローンの集団で,それぞれのクローンは異なるDNA断片の挿入されたベクターを含んでいる.cDNAライブラリーとゲノム DNA ライブラリーの違いは何か。特定の遺伝子をライブラリーから探し出すのに、ハイブリッド形成や発現をどのように使うか。
- Met-Pro-Glu-Phe-Tyr というペプチドをコードしている遺伝子を,ライブラリーからスクリーニングするのに、プローブとしていくつのオリゴヌクレオチドプライマーを合成したらよいか
- 1993年にKerry Mullis はPCR法の開発によりノーベル化学賞を受賞した。PCR反応の各サイクルにおける3段階の操作は何か。好熱性DNA ポリメラーゼ(つまりTagポリメラーゼ)の発見はなぜPCR の開発に重要だったのか。
- サザンプロット法とノーザンプロット法は、核酸のハイプリッド形成に基づく分子生物学の重要な手法である。両者の共通点は何か、相違点は何か。この二つのブロット法の応用例をあげよ.
- 細菌や哺乳類細胞を使って、多数の外来タンパク質の発現が行われている。こうしたタンパク質の発現に使われる組換えプラスミドに必要な要素は何か。精製を容易にするためには、外来タンパク質にどのような修飾をほどこすか。細菌ではなく哺乳類細胞をタンパク質発現に用いる利点は何か。
- DNAマイクロアレイとは何か。遺伝子発現解析にマイクロアレイをどうやって使うか。マイクロアレイとノーザンブロット法を使う実験は何が違うか。
- 新たに発見された遺伝子がコードするタンパク質がどんなものかを決めるには、この遺伝子の発現パターンを解析することが役立つ。たとえば,SERPINA6という遺伝子は、肝臓、腎臓そして膵臓で発現しているが、その他の組織では発現していない。ある遺伝子がどの組織で発現しているかを調べるには、どうしたらよいか。
- DNA多型はDNAマーカーとして利用できる。RFLP、SNP、SSR多型は何が違うか。遺伝子地図作成で、これらマーカーはどのように使われるか。
- 連鎖不平衡という考えに基づいた遺伝子地図作成を行うと、古典的な連鎖解析よりは高分解能で遺伝子の位置を決めることができるが、どのような解析をするか。
- 遺伝連鎖解析によって、病因遺伝子の染色体上のおよその位置は推定できる。連鎖解析で見いだされた領域内で病因遺伝子を同定するのに,発現解析やDNA 配列解析をどのように使うか
- siRNA を使う遺伝子ターゲッティングでは、すべての後生生物にはあるが酵母などの簡単な真核生物にはないマイクロRNA経路を利用する。この経路で、DicerやRISCはどんな役割を果たしているか。
- マウスゲノム中の特定の遺伝子を特異的に修飾する技術によって,マウス遺伝学は革命的な変化を遂げた。特定の遺伝子座についてノックアウトマウスを作製する手順を述べよ。遺伝子のコンディショナルノックアウトを行うのに、IoxP-Cre系をどのように使うか。ノックアウトマウスの医学的応用で重要なものは何か。
- ドミナントネガティブ変異とRNAiは、遺伝子配列を変えずに遺伝子を不活性化する方法である。それぞれの方法が遺伝子発現を阻害するしくみを説明せよ。
遺伝子突然変異によって、複雑な細胞内過程や発生過程の機構を解明することができる。劣性変異と優性変異では、遺伝学的解析にどのような違いが表れるか。
劣性変異と優性変異の違い
| 項目 | 劣性変異 | 優性変異 |
|---|---|---|
| 表現型 | 両方の対立遺伝子が変異型の場合にのみ発現 | 1つの対立遺伝子が変異型でも発現 |
| ヘテロ接合体 | 通常は野生型のまま | 変異型表現型を示すことが多い |
| 機能喪失・獲得 | 多くが機能喪失型(ロスオブファンクション) | 機能獲得型、もしくはドミナントネガティブ型も多い |
| 解析上の扱い | リセスシブスクリーニングが必要 | ドミナントスクリーニングが可能 |
遺伝学的解析における主な違い
劣性変異の場合
- 変異体表現型が出現するのはホモ接合体(両方の遺伝子が変異)だけです。
- F2世代などで1/4の比率で変異型が現れるなど、メンデルの法則に従った分離比が見られます。
- 機能欠失変異によって、ある遺伝子が本来どんな役割を果たしていたかが明らかになります。
- 正常な遺伝子(野生型アレル)が一方にあれば表現型は隠れるため、*サイレントキャリア*が生じやすいです。
優性変異の場合
- ヘテロ接合体でも変異表現型が現れるため、F1世代からすぐに変異の効果を観察できます。
- 表現型の出現率が高く、より迅速なスクリーニングや解析が可能になります。
- 機能獲得型変異や、野生型の機能を抑制・阻害するドミナントネガティブ型変異など、幅広い機構を明らかにしやすいです。
- 遺伝性疾患や形質発現が家系内にすぐ現れることが多いので、ヒト遺伝学でも特徴的です。
まとめ
- 劣性変異はホモ接合体で表現型が現れるため、遺伝子の「機能喪失」の解析や、機能必須性の発見に多用されます。
- 優性変異はヘテロ接合体でも観察できるため、遺伝子機能の獲得やドミナントネガティブ効果など、より多彩な遺伝子作用の解明に有効です。
- このため劣性・優性変異の性質ごとに、異なる遺伝学的解析手法(スクリーニング、分離比の観察、家系解析など)が用いられます。
ポイント
劣性変異は「機能欠失」の確認や正確な遺伝子役割の解析に便利で、優性変異は「機能獲得」や「ドミナント効果」を早期に発見するのに適しています。研究目的や解析対象に応じて両者を使い分けるのが、分子遺伝学の基本です。
必須遺伝子の機能を研究するにあたって、温度感受性変異はなぜ重要か。また、これをどのように利用するか。例をあげよ。
温度感受性変異が重要な理由
- 必須遺伝子の解析が可能になる
必須遺伝子とは、その機能が完全に失われると細胞や生物が生存できなくなる遺伝子です。通常の欠損変異では、変異細胞自体が生存できないため、遺伝子の機能解析が困難です。
温度感受性変異(temperature-sensitive mutation)は、ある温度(許容温度)では正常に機能し、別の温度(非許容温度)では機能が失われる変異です。これにより、生存させたまま任意のタイミングで遺伝子機能を“オン・オフ”できるため、必須遺伝子機能の詳細な解析が可能となります。
温度感受性変異の利用法
- 実験的な温度スイッチとして活用
温度感受性変異株を通常の許容温度で培養し、目的の発生段階や細胞周期、成長段階で非許容温度に移すことで、特定タイミングで遺伝子機能を失わせ、その時点での表現型や細胞の反応を観察できます。このようにして、必須遺伝子が「いつ」「どのような生命現象に必要か」を明らかにできます。 - 時間・空間的な機能制御が可能
機能を急速かつ可逆的に停止させることができるため、細胞分裂、発生、行動、神経系などタイミングや組織による応答が重要な現象の研究に応用されています。 - サプレッサーや協調分子の探索
温度感受性変異株を使って、機能が失われた際に表現型を回復するサプレッサー変異や、関連する遺伝子ネットワーク、薬剤感受性の解析も可能です。
代表的な例
まとめ
- 温度感受性変異は、必須遺伝子の「生存に不可欠な機能」を損なうことなく、任意のタイミングで機能を停止できるため、その遺伝子の正確な役割や働きを明らかにする強力な手法です。
- 細胞周期制御、発生、神経、生殖、行動など幅広い分野で重要な知見が得られており、「動的で不可逆的に失活させる」ための活用例が世界中で蓄積されています。
2つの変異が同じ遺伝子に起こったのか、別の遺伝子に起こったのかを調べるのに、どのように相補性検定を使うか。優性変異ではこれが使えないのはなぜか。説明せよ。
相補性検定(コンプリメンテーションテスト)の使い方
- 目的
2つの変異が「同じ遺伝子」か「異なる遺伝子」に起こっているかを調べる実験手法です。 - 方法の概要
同じ表現型(例:同じ異常や性質)をもつ「ホモ接合性の劣性変異体」同士を掛け合わせ、F1雑種(ヘテロ接合体)の表現型を調べます。 - 判定の仕組み
- <異なる遺伝子の場合(相補)>
片方の親に正常な遺伝子が残っているので、F1雑種には両方の遺伝子の正常コピーが1つずつそろい、「野生型(正常)」の表現型が現れます。 - <同じ遺伝子の場合(非相補)>
どちらの親にも同じ遺伝子の異常型しかないため、F1雑種でも正常機能を持つアレルが1つもなく、「変異型」の表現型が現れます。
- <異なる遺伝子の場合(相補)>
- まとめ表
| F1雑種の表現型 | 変異の位置 | 解釈 |
|---|---|---|
| 正常 | 別の遺伝子(相補) | 変異は異なる遺伝子にある |
| 異常 | 同じ遺伝子(非相補) | 変異は同じ遺伝子にある |
優性変異で相補性検定が使えない理由
- 相補性検定は劣性変異を前提とする理由
- イメージ図(省略)
- 劣性:正常+変異 → 正常表現型(判定可能)
- 優性:正常+変異 → 変異表現型(判定不能)
まとめ
ポイント:
- 同じ表現型の変異体同士を掛け合わせ、F1が正常なら異なる遺伝子、異常なら同じ遺伝子と判別する。
- 優性変異は常に変異表現型が現れるため、相補性検定では判定できません。
抑制変異と合成致死変異の使い方の違いを比較せよ。
定義
- 抑制変異(Suppressor Mutation)
最初の変異によって生じた異常な表現型や機能障害を、第二の変異(抑制変異)が回復または軽減する現象です。抑制変異は同一遺伝子内(イントラジェニック)または異なる遺伝子間(インタージェニック)で生じることがあります。 - 合成致死変異(Synthetic Lethal Mutation)
個々では生存可能な2つ以上の変異が、同時に存在した時にのみ細胞や生物を死に至らせる現象です。
使い方の違い
| 項目 | 抑制変異 | 合成致死変異 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 機能回復メカニズムの解析、遺伝子間の機能的関係の解明 | 冗長性や必須経路の探索、特異的ターゲット治療開発 |
| 解析できる事例 | 異常表現型の回復、抑制の分子機序解明 | 遺伝子間の協調・補完関係、組み合わせ致死性の解明 |
| 遺伝学的判断 | 第二変異で表現型が正常化 | 二重変異体のみが致死 |
| 実験的な活用法 | 変異表現型の抑制・回避を探す | 二重変異の表現型(致死)から関係遺伝子網羅的探索 |
| 応用例 | サプレッサースクリーニング、タンパク質間相互作用探索 | がん治療の標的(合成致死治療)、冗長経路解明 |
詳細な使い方の違い
抑制変異の使い方
- 一度変異で失活させた遺伝子や機能を、サプレッサー(抑制)変異で回復させ、その回復過程や分子レベルの「補償」メカニズムを解析するのに使われます。
- 例:タンパク質構造の変化、tRNA変異によるコドン読み替え、遺伝子間ネットワークの機能代替の発見、経路のバイパス発見。
合成致死変異の使い方
- 2つの異なる遺伝子を同時に変異させたときのみ致死となることから、生命維持に必須な経路や相補経路、遺伝子の「隠れた機能冗長性」を調べる手法です。
- 例:がん細胞である遺伝子が損傷しているとき、別遺伝子を阻害すれば正常細胞は死なないががん細胞だけを死滅できるという合成致死治療。
ポイントまとめ
- 抑制変異は「障害の救済メカニズムや回復パスウェイの解明」に、合成致死変異は「組み合わせによる必須経路や新しい治療標的の探索」に使われる点が最大の違いです。
- 抑制変異による現象回復は、遺伝子間の「機能冗長」や「抑制経路」、「タンパク質同士の相互作用」などを明らかにします。
- 合成致死変異は、単独では表現型が出ない「隠れた機能の協調」を見極める強力なツールであり、特に医学生物学ではがん治療戦略開発に直結します。
制限酵素とDNAリガーゼはDNAクローニングに欠かせない.制限酵素を産生している細菌はなぜ自身のDNAを分解しないのか。制限部位の一般的な特徴をあげよ。制限酵素でDNAを分解したとき生じる、3種類の末端はどんなものか。DNAリガーゼはどんな反応を触媒するか。
制限酵素を産生している細菌はなぜ自身のDNAを分解しないのか
- 制限酵素は、特定の塩基配列(制限部位)を認識しDNAを切断しますが、細菌自身のDNAは認識部位がメチル化されているため、制限酵素による切断を受けません。
- このメチル化修飾は「メチルトランスフェラーゼ」という酵素によって行われ、**制限酵素ごとに対応するメチル化酵素(制限修飾系)**が存在します。
- 外来DNA(ウイルスやファージ由来など)はメチル化されていないため、細菌の制限酵素によって切断されます。
制限部位の一般的な特徴
- パリンドローム(回文)配列
多くの制限酵素(特にII型)は、4~8塩基対からなる配列で、上下鎖が相補的で同じ並びになる回文配列を認識します。 例:EcoRIが認識する5′-GAATTC-3’など。 - 左右対称性、特異的な塩基配列
制限酵素によって認識する配列や切断位置は異なります。
制限酵素でDNAを分解したとき生じる3種類の末端
- 5’突出末端(sticky end, 5′ overhang)
- 3’突出末端(sticky end, 3′ overhang)
- 平滑末端(blunt end)
| 末端の種類 | 形状 | 例 |
|---|---|---|
| 5’突出末端 | 5’側に突出 | EcoRI |
| 3’突出末端 | 3’側に突出 | KpnI |
| 平滑末端 | 突出部なし | SmaI, EcoRV |
DNAリガーゼはどんな反応を触媒するか
- DNAリガーゼは、2本鎖DNAの5’リン酸基と3’ヒドロキシル基をホスホジエステル結合で連結する反応を触媒します。
- この反応によって、切断されたDNA断片同士や岡崎フラグメントなどがつなぎ合わされ、DNA鎖の「ニック」や断片を修復・連結できます。
- クローニング実験では、同じ末端同士のDNA断片を選択的に結合させるために必須の酵素です。
細菌のプラスミドはクローニングベクターに使える。プラスミドベクターで必須な要素は何か。プラスミドをクローニングベクターとして使うときの利点と応用例をあげよ。
プラスミドベクターの必須な要素
- 複製起点(Origin of Replication:ORI)
プラスミドが宿主細胞内で独立して複製されるために必要なDNA配列です。ORIの有無でプラスミドの複製能力やコピー数が決まります。 - 選択マーカー(Selectable Marker)
プラスミドを導入した細胞を他と区別するための遺伝子。代表例は抗生物質耐性遺伝子(アンピシリン耐性など)で、抗生物質を添加した培地中でプラスミドを持つ細胞のみ生き残ります。 - 多重クローニング部位(MCS:Multiple Cloning Site)
複数の制限酵素認識配列を持ち、外来遺伝子を挿入しやすい領域です。これにより思い通りのDNA断片を効率よく組み込めます。 - プロモーター(発現用ベクターの場合)
挿入した遺伝子を発現させる場合、プロモーター領域の有無・種類が重要です(例:T7プロモーターなど)。 - インサート(外来DNA配列)
クローニングの目的に応じて導入したい遺伝子や配列。
| 要素 | 役割・意義 |
|---|---|
| ORI | プラスミド複製の起点 |
| 選択マーカー | プラスミド導入細胞の選択 |
| MCS(多重クローニング部位) | 外来遺伝子挿入の利便性 |
| プロモーター | タンパク質発現用に必要(発現ベクター) |
| 外来DNA(インサート) | 研究・応用の対象遺伝子 |
プラスミドベクター利用の主な利点
- 操作が簡単・扱いやすい
小型かつ環状DNAであり、試験管内での操作や増幅、精製が容易。 - 高い複製効率
宿主細胞内で高コピー数を維持できるので、目的とするDNAの大量生産が可能。 - 選択的な細胞の獲得が容易
抗生物質などで選択的にプラスミド導入細胞のみを生かせる。 - 多様な設計の柔軟性
様々な制限酵素部位や発現制御配列の導入が可能で、研究目的や目的遺伝子に合わせて自由に設計できる。 - 安定性が高い
小型・環状構造により安定しており、分解や損傷を受けにくい。
プラスミドクローニングベクターの応用例
- 遺伝子クローニング
目的遺伝子断片の組換え・増幅やDNAシーケンシング。 - タンパク質発現
バクテリアや酵母などで特定タンパク質を大量作製(例:ヒトインスリンや酵素などの製造)。 - 遺伝子導入実験、機能解析
外来遺伝子の導入による遺伝子機能の解析や細胞の形質転換。 - バイオ医薬・ワクチン開発
治療用タンパク質やワクチン抗原の合成・大量生産、さらには遺伝子治療ベクターの基盤。 - 農業・環境工学
作物の品種改良(遺伝子導入による耐病性・高栄養性の付与)、有用微生物の作出など。
まとめ
プラスミドベクターは、ORI・選択マーカー・MCSなどの基本構造を備えており、操作性の高さや応用の広さから分子生物学・バイオテクノロジー分野で欠かせないツールです。日常的な遺伝子クローニングから応用研究、医薬・農業まで、多様な目的で活用されています。
DNAライブラリーはクローンの集団で,それぞれのクローンは異なるDNA断片の挿入されたベクターを含んでいる.cDNAライブラリーとゲノム DNA ライブラリーの違いは何か。特定の遺伝子をライブラリーから探し出すのに、ハイブリッド形成や発現をどのように使うか。
cDNAライブラリーとゲノムDNAライブラリーの違い
- cDNAライブラリーは、細胞のmRNAを逆転写酵素でcDNA(相補的DNA)に変換し、ベクターに組み込んだものです。イントロンが除かれており、実際に発現した遺伝子のみが含まれます。組織や発生段階ごとの遺伝子発現解析や、タンパク質発現、機能解析に適しています。
- ゲノムDNAライブラリーは、生物のゲノム全体を細かく切断し、ベクターに組み込んだものです。遺伝子部分だけでなく、イントロン、調節領域、非コード領域もすべて網羅します。遺伝子の構造解析やゲノム配列決定などに用います。
特定の遺伝子をライブラリーから探し出す方法
ハイブリッド形成法(ハイブリダイゼーション)
- 原理と流れ
- 特徴
- 塩基配列の相補性を利用するため、対象遺伝子が既知の配列情報をもとに迅速に検出できる。
- ゲノムDNAライブラリー、cDNAライブラリーどちらにも応用可能。
発現スクリーニング法(発現クローン化)
- 原理と流れ
- 特徴
- 遺伝子配列が未知でも、タンパク質機能や特異抗体があれば目的クローンを同定できる。
- 主にcDNAライブラリーで利用される。
まとめ
- cDNAライブラリーは「発現している遺伝子のみ」「イントロンなし」,ゲノムDNAライブラリーは「全遺伝子+調節・非コード領域」「イントロンあり」という違いがあります。
- 特定遺伝子の探索には、ハイブリッド形成による配列のスクリーニング、または発現スクリーニングによるタンパク質機能や抗体反応を利用した方法が用いられます。
こうした手法を駆使することで、目的の遺伝子やその発現産物の分子生物学的解析が効率的に進められます。
Met-Pro-Glu-Phe-Tyr というペプチドをコードしている遺伝子を,ライブラリーからスクリーニングするのに、プローブとしていくつのオリゴヌクレオチドプライマーを合成したらよいか
コドンの組み合わせ数を求める方法
アミノ酸配列Met-Pro-Glu-Phe-Tyrをコードする塩基配列は、各アミノ酸が複数のコドンに対応しているため、多数の組み合わせが存在します。オリゴヌクレオチドプローブ(プライマー)を合成する場合、すべてのコドン組み合わせをカバーする必要があります。
各アミノ酸のコドン数
| アミノ酸(略号) | コドン数 | 具体的なコドン |
|---|---|---|
| Met(メチオニン) | 1 | ATG |
| Pro(プロリン) | 4 | CCT, CCC, CCA, CCG |
| Glu(グルタミン酸) | 2 | GAA, GAG |
| Phe(フェニルアラニン) | 2 | TTT, TTC |
| Tyr(チロシン) | 2 | TAT, TAC |
全組み合わせ数の計算
- Met: 1通り
- Pro: 4通り
- Glu: 2通り
- Phe: 2通り
- Tyr: 2通り
したがって、
1 × 4 × 2 × 2 × 2 = 32通り の異なるオリゴヌクレオチド配列が考えられます。
結論
Met-Pro-Glu-Phe-Tyr をコードする遺伝子をスクリーニングするために必要なオリゴヌクレオチドプローブ(プライマー)の数は 32本です。
補足
- 実際には配列の中で制限酵素部位や他の配列情報が既知の場合、組み合わせをさらに絞り込むことができます。
- できるだけ組み合わせ数を減らしたい場合は、アミノ酸のうちコドンが少ない部分や保存配列を選ぶことが重要です。
1993年にKerry Mullis はPCR法の開発によりノーベル化学賞を受賞した。PCR反応の各サイクルにおける3段階の操作は何か。好熱性DNA ポリメラーゼ(つまりTagポリメラーゼ)の発見はなぜPCR の開発に重要だったのか。
PCR反応の各サイクルにおける3段階の操作
PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)は、DNAの特定配列を短時間で大量に増幅する技術です。1サイクルあたり、次の3つの基本ステップからなります。
- 変性(Denaturation)
- 約94~98°Cで行われる。
- 二本鎖DNAを一本鎖に“解離”(水素結合の切断)させるための高温処理。
- アニーリング(Annealing)
- 約50~65°Cで行われる(プライマーの設計によって最適温度は調整)。
- 合成したオリゴヌクレオチドプライマーが一本鎖DNA上の相補配列に特異的に結合(アニーリング)する。
- 伸長(Extension, Elongation)
- 約72°Cで行われる(Tagポリメラーゼの最適温度)。
- DNAポリメラーゼがプライマーから新しいDNA鎖を5’→3’方向に合成し、目的配列のコピーを作る。
この3段階を1サイクルとし、20~40回繰り返すことで、特定DNA配列を指数関数的に増幅できます。
好熱性DNAポリメラーゼ(Tagポリメラーゼ)の発見がPCR開発に重要だった理由
- 高温を維持する工程に耐える酵素
- PCRの「変性」段階では毎回94~98°Cの高温になるため、普通のDNAポリメラーゼ(例:E. coli 由来)はタンパク質が熱変性し失活してしまいます。そのため、最初期には各サイクルごとに新しい酵素を追加する必要があり、手間もコストも非常に高くなっていました。
- Tagポリメラーゼの登場
- ターマス・アクアティクス(Thermus aquaticus)という高温環境に生息する細菌から抽出されたDNAポリメラーゼ(Tagポリメラーゼ)は、90°Cを超える高温でも活性を維持できます。
- これにより、「1度の酵素添加で、何十サイクルも連続して自動的に反応が進行する」ことが可能になりました。全自動PCR装置による大量のDNA増幅が現実的になって、PCRは一躍、基礎から応用分野まで幅広く使われる画期的な技術となりました。
- 革命的な進歩の要因
- Tagポリメラーゼの発見によって、PCRは“簡便・迅速・高感度”かつ“自動化”が実現し、世界中の分子生物学実験の常識を大きく変えることとなりました。
まとめ
- PCR反応の各サイクルは「変性」「アニーリング」「伸長」の三段階。
- 好熱性DNAポリメラーゼ(Tag)は、高温にも耐える酵素であり、PCRを効率的・自動的に進行させるために不可欠な発見だった。
Tagポリメラーゼがなければ、PCRの普及や分子生物学の飛躍的発展は不可能だったと言えます。
サザンプロット法とノーザンプロット法は、核酸のハイプリッド形成に基づく分子生物学の重要な手法である。両者の共通点は何か、相違点は何か。この二つのブロット法の応用例をあげよ.
共通点
- 核酸のハイブリッド形成を利用
どちらも標的となる塩基配列と、相補的なプローブ分子(DNAまたはRNA)をハイブリダイズ(結合)させて検出を行う手法です。 - 電気泳動による分離
サンプル内の核酸断片をアガロースゲル電気泳動などでサイズごとに分離してから分析します。 - メンブレンへの転写(ブロッティング)
電気泳動した核酸断片をニトロセルロース膜やナイロン膜などのメンブレンに転写します。 - 標識プローブによる検出
放射性同位体や蛍光標識などによって可視化します。 - 高い特異性
相補的な塩基配列同士が特異的に結合する性質を利用するため、目的配列だけを選択的に検出可能です。
相違点
| サザンプロット法 | ノーザンプロット法 | |
|---|---|---|
| 検出対象 | DNA(主にゲノムDNA断片) | RNA(主にmRNA。rRNA, tRNAにも応用) |
| プローブ | 主にDNAプローブ | DNAまたはcDNAプローブ |
| 解析の目的 | 遺伝子の有無・構造、遺伝子多型や変異の検出 | 遺伝子発現の有無・発現量、mRNAのサイズ検出 |
| サンプル処理 | 2本鎖DNAを制限酵素で切り分けて分析 | 抽出したRNAをそのまま分析 |
| 考案者・命名 | E. M. Southern(名前由来) | サザンにちなみジョーク的な命名 |
| サイクルや温度 | 塩基性溶液で二本鎖を一本鎖化し転写 | RNAは一本鎖なので特別な変性処理不要 |
応用例
サザンプロット法の応用例
- 遺伝子変異の検出・遺伝子診断
遺伝性疾患やがんなどで遺伝子変異や欠失、挿入、リピート配列の検出(例:遺伝子型判定、DNAフィンガープリント)。 - DNAメチル化解析
メチル化感受性制限酵素との組み合わせでエピジェネティクス研究に応用。 - 品種鑑定・個体識別
植物や動物の品種判定、親子判定、法医分野(指紋DNA解析)。
ノーザンプロット法の応用例
- 遺伝子発現解析
mRNAの発現レベルやサイズ検出(特定組織・疾患・発生段階ごとの比較など)。 - 遺伝子の発現パターン解析
形態形成・細胞分化・疾患発症時の遺伝子発現変動の解析。 - 異常な転写産物の検出
異なるスプライシングバリアントや異常mRNA検出(例:がん関連RNA、分化マーカーなど)。
まとめ
- サザンプロット法とノーザンプロット法は、どちらも核酸のハイブリダイゼーション原理に基づく、特異的かつ高感度な解析法です。
- 最大の違いは**「DNA解析」か「RNA解析」か**という対象部分にあります。
- 両者とも、分子生物学・医学・遺伝子工学など多様な分野で基本かつ応用範囲の広い技術です。
| 手法 | 主な対象 | 主な用途 |
|---|---|---|
| サザンプロット | DNA | 遺伝子変異/多型・DNA解析 |
| ノーザンプロット | mRNA(RNA) | 遺伝子発現解析・発現パターン |
細菌や哺乳類細胞を使って、多数の外来タンパク質の発現が行われている。こうしたタンパク質の発現に使われる組換えプラスミドに必要な要素は何か。精製を容易にするためには、外来タンパク質にどのような修飾をほどこすか。細菌ではなく哺乳類細胞をタンパク質発現に用いる利点は何か。
組換えプラスミドに必要な要素
- 複製起点(Origin of Replication, ORI)
プラスミドが宿主細胞内で複製されるために必要。細菌・哺乳類細胞用で異なるORIsが使われる。 - 選択マーカー遺伝子
プラスミドを導入した細胞を選别するための遺伝子。細菌なら抗生物質耐性遺伝子(例:アンピシリン耐性)、哺乳類細胞ならネオマイシン耐性(G418耐性)などが使われる。 - プロモーター・エンハンサー配列
外来遺伝子が効率よく発現するための制御配列。細菌ならlacプロモーターやT7プロモーター、哺乳類細胞ならCMVプロモーターなど。 - 多重クローニング部位(Multiple Cloning Site, MCS)
外来遺伝子を容易に挿入できるよう複数の制限酵素部位がまとめて配置されている。 - ポリA付加配列や終止シグナル
mRNAの安定性や翻訳効率向上のために必要(特に哺乳類細胞で重要)。 - タグ配列や精製用シーケンス
精製や検出用の配列挿入に対応した構造。
精製を容易にするための外来タンパク質への修飾
- アフィニティータグ(タグ配列)の付加
- Hisタグ(ヒスチジンタグ):6×Hisなどの配列をN末端やC末端に連結。ニッケルカラムで特異的に精製可能。
- FLAGタグ、HAタグ、Mycタグ:抗体による検出・精製に使うペプチドタグ。
- GSTタグ:グルタチオンSトランスフェラーゼとの融合で、グルタチオンアフィニティーカラムで精製可。
- Protein Aタグなど:他の分子との結合性を利用した精製も可能。
- プロテアーゼ切断部位の導入
- 精製後にタグを除去するため、タグと本体の間にプロテアーゼ認識配列を挿入する方法が取られる。
細菌ではなく哺乳類細胞をタンパク質発現に用いる利点
- 翻訳後修飾が行える
- 糖鎖付加(グリコシル化)、リン酸化、アセチル化、メチル化など、真核生物特有の翻訳後修飾を再現できる。
- 正常な立体構造や酵素活性、生理的活性が維持されやすい。
- 複雑なタンパク質や膜タンパク質の発現が可能
- 細菌では構造が崩れたり不溶化しやすい複雑なタンパク質も、哺乳類細胞なら正常に発現することが多い。
- 毒性タンパク質や分泌タンパク質の発現効率向上
- 細胞外への分泌や、細胞表面の局在など、生物学的に重要な機能も含めて正確に再現可能。
- ヒト由来タンパク質の医薬品開発に有利
- 医薬用抗体や治療用タンパク質の開発時に、ヒト細胞での発現系は安全性・機能性チェックにも適している。
まとめ表
| 要素 | 細菌発現系 | 哺乳類細胞発現系 |
|---|---|---|
| 翻訳後修飾 | 限定的 | 可能・多様 |
| 精製タグ | 使用可 | 使用可 |
| 発現効率 | 高い | やや低いが安定 |
| 発現できるタンパク質 | 比較的単純 | 複雑なタンパク質も可 |
| 応用例 | 研究用タンパク質、大量合成 | 生物活性タンパク質、医薬品 |
哺乳類細胞を使う発現系は、ヒトでの機能解析や医薬品開発など、より“生物学的に自然な”タンパク質生成に強みがあります。
DNAマイクロアレイとは何か。遺伝子発現解析にマイクロアレイをどうやって使うか。マイクロアレイとノーザンブロット法を使う実験は何が違うか。
DNAマイクロアレイとは何か
DNAマイクロアレイは、数千から数万種類のDNAプローブ(短い一本鎖DNA断片)がガラススライドやチップ上に高密度で固定された解析装置です。各プローブは特定の遺伝子配列に対応しており、サンプル中のmRNA(遺伝子発現)やゲノムDNA配列の網羅的な検出が一度に可能です。
遺伝子発現解析にマイクロアレイをどうやって使うか
- mRNAからcDNAを作製
サンプル(例:がん細胞と正常細胞や異なる組織)から抽出したmRNAを、逆転写酵素を使ってcDNA(相補的DNA)に変換します。
異なるサンプルには、それぞれ異なる蛍光色素などで標識します。 - マイクロアレイへのハイブリダイゼーション
蛍光標識したcDNAをマイクロアレイ上に加え、固定された各プローブと相補的に結合させます。 - 蛍光シグナルの検出・解析
結合したcDNAの蛍光強度を専用スキャナーで読み取ることで、各遺伝子の発現量を同時かつ定量的に測定できます。 - 発現パターンの比較
正常細胞とがん細胞、異なる発生段階やストレス応答時など、さまざまな条件間で数千~数万遺伝子の発現プロファイルを一度に比較できます。
マイクロアレイとノーザンブロット法の違い
| 項目 | DNAマイクロアレイ | ノーザンブロット法 |
|---|---|---|
| 一度に調べる遺伝子数 | 数千~数万 | 1~数種類 |
| サンプル量・感度 | 微量、高感度 | 比較的多量、感度は中程度 |
| 定量性・網羅性 | 定量的かつ網羅的な発現比較が可能 | 半定量的、特定遺伝子の検出向き |
| 解析できる情報 | 全遺伝子発現プロファイル・発現パターン | ターゲット遺伝子の発現量やスプライシングバリアント |
| 準備・コスト | 高度な装置と費用が必要 | 比較的簡便、安価 |
| 特徴的な応用 | 疾患マーカー探索、発現パターン分類、創薬 | 特定遺伝子の発現確認や異常検出 |
- **DNAマイクロアレイ**は、全遺伝子規模で発現量の網羅解析ができ、複数条件間の比較や疾患バイオマーカー探索、発現パターンによるクラスター分析などに広く用いられます。
- **ノーザンブロット法**は、あらかじめ標的を絞った“特定の遺伝子”のmRNA量やスプライシング異常の検出など、詳細な発現解析や検証実験に適しています。
要点まとめ
- マイクロアレイは膨大な遺伝子の同時解析が可能な“網羅的”手法です。
- ノーザンブロット法は、少数の遺伝子を“高い特異性”で解析する伝統的な方法です。
- 比較すると、スケール・目的・解析情報が大きく異なります。
新たに発見された遺伝子がコードするタンパク質がどんなものかを決めるには、この遺伝子の発現パターンを解析することが役立つ。たとえば,SERPINA6という遺伝子は、肝臓、腎臓そして膵臓で発現しているが、その他の組織では発現していない。ある遺伝子がどの組織で発現しているかを調べるには、どうしたらよいか。
遺伝子の組織発現パターンを調べる主な方法
- RT-PCR法(逆転写PCR)
各組織からRNAを抽出し、遺伝子特異的プライマーでRT-PCRを行うことで、その遺伝子mRNAがあるかどうかを調べることができます。
複数の組織サンプルを比較することで、どの組織で発現しているかを確認できます。 - ノーザンブロット法
各組織から抽出したRNAを電気泳動し、ターゲット遺伝子に特異的なプローブとハイブリダイズさせてmRNA量を可視化します。これにより発現組織とおおよその量的違いも分かります。 - in situ ハイブリダイゼーション
組織切片上で遺伝子特異的プローブを使い、mRNAの局在を直接観察できる方法です。組織内のどの細胞や部位で発現しているかまで可視化できます。 - 定量的リアルタイムPCR(qRT-PCR)
各組織サンプルでmRNA量を高感度かつ定量的に比較できます。複数組織間の発現量の細かな違いを調べる場合に有用です。 - マイクロアレイ解析
数千~数万の遺伝子の発現量を同時に解析できる網羅的手法です。新規遺伝子が載っていれば組織発現プロファイルを一度に比較可能です。 - RNA-Seq(次世代シーケンスによる網羅的発現解析)
近年よく使われる手法で、各組織ごとのRNAを高精度で定量的に解析できます。新しい遺伝子やスプライシングバリアントも検出可能です。 - バイオインフォマティクスデータベースの活用
GTEx(Genotype-Tissue Expression)など、ヒト遺伝子の組織別発現データベースが公開されています。遺伝子名を入力すれば各臓器・組織での発現量情報を調べることができます。
実験例と選択のポイント
- 新たに発見された遺伝子の場合は、まずRT-PCRやノーザンブロット法で主要な組織のmRNA発現を確認し、より詳細な局在や量を知りたい時はin situ hybridizationやqRT-PCR、RNA-Seqを利用するのが効果的です。
- 利便性や予算、解析したい遺伝子数に合わせて手法を選ぶのが一般的です。
まとめ
1つの遺伝子がどの組織で発現しているかを調べるには、RNAレベルでの発現解析法(RT-PCR、ノーザンブロット法、qRT-PCR、in situハイブリダイゼーション、マイクロアレイ解析、RNA-Seqなど)を活用します。実験的手法に加え、既存のデータベース検索も便利です。分析目的や必要な情報に応じて、最適な方法を選択してください。
組織特異的遺伝子発現解析の手法
- 公共データベース解析(バイオインフォマティクス)
- qPCR(リアルタイム定量PCR)による発現量解析
- マイクロアレイあるいはRNA-Seqによる網羅的発現解析
- in situハイブリダイゼーション(ISH)による組織切片レベルの解析
このように、データベース検索→qPCR→網羅的解析→組織局在解析、という順で進めると効率的で確実です。既存情報を活用しつつ、必要に応じて実験的検証を追加します。
DNA多型はDNAマーカーとして利用できる。RFLP、SNP、SSR多型は何が違うか。遺伝子地図作成で、これらマーカーはどのように使われるか。
RFLP、SNP、SSR多型の違い
詳細解説
- RFLP(制限酵素断片長多型)
DNA断片を制限酵素で切断し、長さの違い(多型)を比較します。多型は主に塩基配列の違いで制限酵素認識部位が消失・新生することで生じます。 - SNP(一塩基多型)
ゲノム中の1塩基だけが個体差(多型)となるもの。多種類検出でき、遺伝子座あたりの情報量は少ないが全ゲノム規模で用いると識別性が高まる。 - SSR(シンプルシークエンスリピート)
2〜6塩基程度の短い配列が繰り返される領域で、繰り返し回数の個体差(長さの違い)が多型となります。複数アリールが存在し、解析感度が高い。
遺伝子地図作成でのマーカー利用法
- 原理
DNA多型マーカー(RFLP, SNP, SSRなど)は個体間・品種間のゲノム領域の違いを「目印=マーカー」として利用できます。 - 地図作成手順と役割
- 両親系統間で区別可能なマーカーを複数選定
- ハイブリッドや交配後代集団全体にわたってマーカー多型の「分離様式」を調査
- マーカー間の「組換え率(遺伝距離)」を計算し、染色体上の並び順や間隔=**遺伝子地図(連鎖地図)**を作成
- 地図上で農業形質・疾患遺伝子などとの関連位置(連鎖解析/QTL解析)も特定可能
- 利用目的
- 対象形質(例:病害抵抗、品質など)がどの遺伝子上かをマーカー情報から予測
- 育種・品種選抜、親子判定や個体識別への応用
- 大規模なゲノム育種、機能遺伝子解析、進化・集団遺伝学への利用
各マーカーの特徴と地図作成での使い分け
| マーカー | 特徴 | 地図作成での利用ポイント |
|---|---|---|
| RFLP | 分解能中、作業量多 | 最初期の地図作成に利用、多型が少なめ |
| SNP | 情報量は1ヶ所あたり少なめ、高頻度 | 全ゲノムマーカー密度向上、自動化・網羅解析に適する |
| SSR | 高多型・高解像度、共優性 | 細かい領域での精密地図、個体識別や親子鑑定 |
まとめ
- RFLPは配列や構造(制限酵素部位)の違い、SNPは1塩基単位、SSRは配列繰り返し回数の違いを検出します。
- これらのマーカーを用いて遺伝的連鎖地図を作成し、目的遺伝子や形質の位置特定、育種選抜、ゲノム解析などに広く活用されています。
連鎖不平衡という考えに基づいた遺伝子地図作成を行うと、古典的な連鎖解析よりは高分解能で遺伝子の位置を決めることができるが、どのような解析をするか。
連鎖不平衡(LD)解析の流れ
- 大量のSNP(一塩基多型)やマーカーを集団規模でゲノム全体に配置し、各マーカー間の連鎖不平衡の度合いを網羅的に計算する
連鎖不平衡とは、2カ所以上の遺伝子座の対立遺伝子の組み合わせ頻度が「独立の期待値」と異なる現象で、染色体上で組換えが起きにくい場合に高い値となります。 - ゲノムワイド関連解析(GWAS)や疾患集団と健常集団を比較し、特定表現型(疾患・性質)に関連するSNPやマーカ一を探す
関連するマーカーと疾患等の間に強い連鎖不平衡がある場合、その周辺に原因遺伝子が存在すると推定できます。
実際にはカイ二乗検定や相関係数、LD値(D’, r²など)を利用してマーカー間の関連度を解析します。 - 連鎖不平衡の高い領域(ハプロタイプブロック)を特定し、範囲を絞り込む
原因遺伝子は、強いLDを示す領域と一致することが多いため、この領域内をさらに精査して詳細位置を推定します。「関連解析」「LDマッピング」「ファインマッピング」とも呼ばれます。 - 集団データを使うため、高分解能の位置決定が可能
古典的な連鎖解析(家系ごとの組換え追跡)は、検出能力が染色体の1cM程度(数百万塩基対単位)に限られますが、LDを利用した地図作成では、数千~数万塩基対単位までピンポイントで原因領域を探索できます。
解析例フロー
- 集団(コホートや症例群)ごとに多数のSNPやマーカーをタイピング
- それぞれのマーカー間のLD値(D’、r²など)を計算し、ゲノム地図にプロット
- 病気表現型や特性と関連するマーカーを統計学的に探索
- 強いLDが検出された領域(ハプロタイプブロック)をさらに詳細解析(候補遺伝子の決定など)
連鎖不平衡解析と古典的連鎖解析の違い
| 比較項目 | 連鎖不平衡解析 | 古典的連鎖解析 |
|---|---|---|
| 解析対象 | 集団データ・非家系(症例対照、GWASなど) | 家系データ(親子・兄弟姉妹関係) |
| 分解能 | 高い(kb~Mbレベル) | 比較的粗い(cMレベル) |
| 用途 | 複雑疾患・微細な領域決定 | 単一遺伝病、家系に限定されがち |
| 必要な情報 | 多数サンプルからの多型データ | 家系図・表現型・遺伝データ |
| 地図精度 | LDブロックごとに範囲を絞り込むため高分解能 | 大まかな組換え率から範囲推定 |
まとめ
- 連鎖不平衡を利用した遺伝子地図作成では、症例・対照集団を中心に、マーカー間のハプロタイプ頻度や連鎖不平衡度合い(D’、r²など)を網羅的に計算し、疾患や形質と高い関連を示す領域を高分解能で絞り込みます。
- そのため、従来よりもきめ細かな位置特定が可能となり、原因遺伝子探索や疾患リスク推定、新規バイオマーカー開発など様々な応用が進んでいます。
遺伝連鎖解析によって、病因遺伝子の染色体上のおよその位置は推定できる。連鎖解析で見いだされた領域内で病因遺伝子を同定するのに,発現解析やDNA 配列解析をどのように使うか
病因遺伝子同定のための発現解析の活用法
- 候補遺伝子の絞り込み
- 連鎖解析で特定された染色体領域には、複数の遺伝子が含まれているのが一般的です。
- 対象となる疾患が主に発症する組織や細胞で「どの遺伝子が発現しているか」を調べることで、その疾患に関係する可能性が高い遺伝子を絞り込むことができます。
- 例:筋疾患の原因遺伝子を探す場合、筋肉組織で強く発現している遺伝子が有力候補となります。
- 発現パターンの比較による異常検出
- 患者と健常者、あるいは病変組織と正常組織でのmRNA発現量を比較し、異常な発現がみられる遺伝子を特定する方法です。
- 発現解析にはRT-PCR、ノーザンブロット、マイクロアレイ、RNA-Seqなどが使われます。
病因遺伝子同定のためのDNA配列解析の活用法
- 全候補遺伝子の構造・配列決定
- 連鎖解析領域にあるすべての候補遺伝子の塩基配列を決定し、患者と健常者で配列の違いを詳しく調べます。
- 特にエクソン領域やスプライス部位、プロモーター領域に着目して解析します。
- 原因変異の発見
- 患者のサンプルで特定の遺伝子にミスセンス変異、ナンセンス変異、フレームシフト変異など、機能に影響する変異が検出されれば、その遺伝子が病因遺伝子である可能性が高まります。
- 健常者にその変異がなく、複数患者に同じ変異や領域で変異が見つかることが重要な証拠になります。
- 次世代シーケンサー(NGS)の利用
- 領域全体や候補遺伝子群のエクソンシークエンスを一度に解析できるため、短期間で多数サンプルの配列比較が可能です。
遺伝子同定の標準的な流れ
- 連鎖解析で原因領域を特定
- その領域内の遺伝子一覧を作成
- 発現解析で組織特異性や疾患関連性の高い遺伝子を絞り込む
- DNA配列解析で患者特異的な変異があるか調べる
- 変異の機能評価(たとえばトランスフェクション実験や動物モデル作成など)で病因性を最終的に検証する
まとめ
- 発現解析は「候補遺伝子の数を大きく絞り込む」役割を担い、DNA配列解析は「実際の原因遺伝子/変異の直接的な同定」を担います。
- 両者を組み合わせることで、連鎖解析だけでは絞りきれない病因遺伝子の同定を効率良く実現できます。
siRNA を使う遺伝子ターゲッティングでは、すべての後生生物にはあるが酵母などの簡単な真核生物にはないマイクロRNA経路を利用する。この経路で、DicerやRISCはどんな役割を果たしているか。
Dicerの役割
- Dicer(ダイサー)はRNase IIIファミリーのエンドリボヌクレアーゼであり、マイクロRNA(miRNA)経路やsiRNA経路の中心的酵素です。
- miRNA前駆体(pre-miRNA)や長い二本鎖RNA(dsRNA)を切断し、約21~23塩基の小さな二本鎖RNA(成熟miRNAやsiRNA)を生成します。
- この“ダイス”反応によって生じた小RNAは、次のRISC(RNA誘導サイレンシング複合体)に取り込まれるための準備が整います。
- Dicerによるこの処理は、標的mRNAに特異性を持たせた抑制を実現する上で不可欠です。
RISCの役割
- RISC(RNA-induced silencing complex、RNA誘導サイレンシング複合体)は、miRNAおよびsiRNAからなる一本鎖RNAと多数のタンパク質で構成される分子複合体です。
- Dicerから提供された小RNAの一方の鎖(ガイド鎖)がRISCに組み込まれ、もう一方は除去されます。
- RISCの中心成分はArgonaute(AGO)タンパク質で、ガイド鎖を頼りに相補的なmRNA配列を探索し結合します。
RISC作用のメカニズム
- 完全相補性があれば(siRNAによる場合)、AGO2が標的mRNAを切断・分解します。
- 不完全相補性(主にmiRNAによる場合)では、mRNAの翻訳抑制や脱アデニル化・デキャッピングを介した安定性低下による分解を引き起こします。
- 一つのRISC複合体は繰り返し標的mRNAに結合し、その発現を強力に抑制します。
まとめ
| 分子 | 主な役割 |
|---|---|
| Dicer | pre-miRNAや長鎖二本鎖RNAを21-23塩基小RNAに切断し、miRNA/siRNAを生成する |
| RISC | 選択されたガイド鎖を取り込み、Argonauteを中心にmRNAを認識・抑制する |
- DicerはmiRNA/siRNA経路の起点となる小RNAの生成、RISCはターゲットmRNAの特異的な抑制を担います。
- この仕組み(RNA干渉)はsiRNAによる遺伝子ノックダウンや細胞の遺伝子調節など幅広い研究・応用に活用されています。
マウスゲノム中の特定の遺伝子を特異的に修飾する技術によって,マウス遺伝学は革命的な変化を遂げた。特定の遺伝子座についてノックアウトマウスを作製する手順を述べよ。遺伝子のコンディショナルノックアウトを行うのに、IoxP-Cre系をどのように使うか。ノックアウトマウスの医学的応用で重要なものは何か。
特定の遺伝子座についてノックアウトマウスを作製する手順
- 標的遺伝子の設計(ターゲティングベクターの作成)
- 目的とする遺伝子の一部を破壊する遺伝子改変用のDNA断片(ターゲティングベクター)を設計し、抗生物質耐性遺伝子(選択マーカー)なども組み込む。
- 胚性幹細胞(ES細胞)への導入
- ターゲティングベクターをマウスES細胞に導入し、相同組換えによって標的遺伝子を改変する。
- 選択・スクリーニング
- 相同組換えが起こったES細胞だけが生き残るよう選択し、さらにPCRやサザンブロット法などで正確にターゲットがノックアウトされているか確認する。
- キメラマウスの作製
- 選択されたES細胞をマウス初期胚に注入し、代理母に戻して発生させると「キメラマウス」が得られる。
- ノックアウトマウスの樹立
- キメラマウスから生殖細胞系列で遺伝子改変を受け継ぐマウスを選び、交配を通じて全身にノックアウトがホモ接合体として発現するマウス(ノックアウトマウス)を得る。
IoxP-Cre系によるコンディショナルノックアウト
- IoxP配列
標的遺伝子の両側にIoxP配列(34塩基対の特殊な認識サイト)を挿入した“フロックスドアレル(floxed allele)”を作成する。 - Creリコンビナーゼの導入
別にCreリコンビナーゼ遺伝子を持つマウス系統を準備し、特定のプロモーターにより組織特異的または誘導的にCreを発現させる。 - 組換え反応
フロックスドアレルマウスとCre発現マウスを交配すると、Creが発現した細胞でIoxP配列間のDNA断片が切り取られ、標的遺伝子が部分的または全域でノックアウトされる。 - メリット
この方法を使うことで「生存に必須な遺伝子」や「特定の時期や組織でだけ機能させたい遺伝子」の機能解析が可能となる。
ノックアウトマウスの医学的応用で重要なもの
- ヒト疾患モデル動物の作製
- 遺伝子の欠損による発症メカニズムの解析や病態の模倣(モデル化)が可能で、がん、糖尿病、筋ジストロフィー、アルツハイマー病、免疫疾患など多数の疾患モデルが開発されている。
- 新規治療法・薬剤開発
- 特定の遺伝子変異があるマウスを使って新たな治療薬の効果・副作用を検証したり、分子標的治療候補遺伝子の探索を行える。
- 遺伝子機能の解明と個別化医療
- ノックアウトマウスによる解析から、遺伝子と疾患・生理現象の因果関係を明らかにすることで、個別化医療(プレシジョンメディシン)への道が広がる。
- 再生医療・幹細胞研究
- 細胞分化や組織再生に関与する遺伝子の機能解明、安全性評価のためのモデルとしても活用されている。
これらの技術と応用により、マウス遺伝学は「疾患の原因解明」「創薬」「分子医学生物学分野の進展」にとって不可欠な基盤となっています。
ドミナントネガティブ変異とRNAiは、遺伝子配列を変えずに遺伝子を不活性化する方法である。それぞれの方法が遺伝子発現を阻害するしくみを説明せよ。
ドミナントネガティブ変異による遺伝子発現阻害のしくみ
- **ドミナントネガティブ変異(Dominant Negative Mutation)**は、正常な遺伝子と同時に存在しても、変異型タンパク質が正常タンパク質の機能を阻害する現象です。
- この方法は遺伝子配列自体は変えずに、外から“機能を持たないか、または異常な構造をもつタンパク質”を過剰に発現させることで作用します。
しくみの例
- 多くのタンパク質は「ホモダイマー」や「多量体」を形成して機能しますが、変異タンパク質が正常タンパク質と結合すると、複合体全体の機能を妨げます。
- たとえば、DNA結合タンパク質や受容体、酵素などがこの影響を受けやすいです。
- ドミナントネガティブ変異体は、正常タンパク質の働きを物理的・立体構造的に阻害したり、複合体全体の機能不全を誘発します。
ポイント
- 通常のアレルが存在していても、変異体タンパク質が「支配的(ドミナント)」に機能阻害を及ぼす。
- 組換えDNA技術を使い、一時的かつ選択的に発現させて使うことが多いです。
RNAi(RNA干渉)による遺伝子発現阻害のしくみ
- **RNAi(RNA interference, RNA干渉)**は、対象遺伝子のmRNAを分解または翻訳抑制することで遺伝子の発現を抑える現象です。
- 遺伝子配列そのものは変えず、**二本鎖RNAやsiRNA(small interfering RNA)、shRNA(small hairpin RNA)**などを導入することで起こります。
しくみの例
- siRNAやshRNAは細胞内のDicer酵素によって切断され、RISC複合体に取り込まれます。
- ガイド鎖となったRNAは、標的mRNAと相補的に結合し、RISCが標的mRNAを切断・分解したり、翻訳を抑制します。
- これによりmRNAレベルで遺伝子発現が効果的にダウンレギュレートされます。
ポイント
- 対象mRNAにのみ特異的に作用し、遺伝子配列を組換えたり変異させる必要がない。
- 数日間から数週間程度、一時的に遺伝子を不活性化する目的で広く使われます。
まとめ表
| 手法 | 阻害のしくみ | 主な利用例・特徴 |
|---|---|---|
| ドミナントネガティブ変異 | 変異タンパク質が正常タンパク質の機能を阻害 | 多量体タンパク質や複合体の機能解析 |
| RNAi | 小分子RNAがmRNA分解や翻訳抑制を誘導 | mRNAレベルで広範な遺伝子ノックダウン |
両者はいずれも**遺伝子配列の改変を行わずに、機能的な不活性化(=ノックダウン)**を実現する代表的な方法であり、分子機能解析・モデル作成・創薬研究など幅広い分野で利用されています。
問題文引用元:東京化学同人 分子細胞生物学 第6版
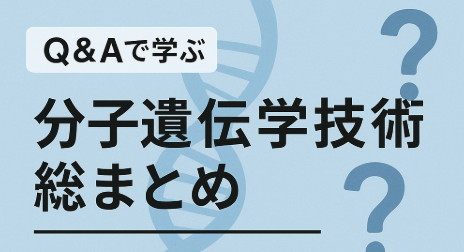
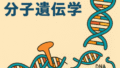
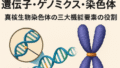
コメント